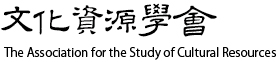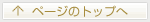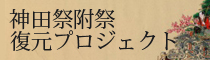第36回 芳春の遠足 「慶應義塾大学日吉キャンパス 旧帝国海軍連合艦隊司令部跡を歩く」
日程
- 2010年3月31日(水)
案内人
- 三浦伸也(東京大学大学院情報学環・学際情報学府博士課程)
解説者
- 喜田美登里(日吉台地下壕保存の会)

慶應義塾大学日吉キャンパスの地下には今も、旧帝国海軍連合艦隊司令部などがおかれた延長1200メートルの巨大地下壕が眠っています。十五年戦争の末期、海軍は海から陸にあがり、連合国軍の本土空襲や本土上陸に備えていました。地下壕は幅約40センチのコンクリートブロックなどで頑強に作られおり、地上にはキノコのような形をした分厚いコンクリート構造物「耐弾式竪穴抗」も見られます。
1944年3月、海軍軍令部第三部が慶應義塾大学日吉キャンパス第一校舎に入り、敵国情報を収集分析していました。同年7月にサイパン島が陥落すると、日吉台国民学校も学童疎開を余儀なくされ、学校は子どもたちが出て行った後に海軍省人事局功績調査部の兵舎となり、次いでそれまで慶應の学生が使っていた寄宿舎が連合艦隊司令部として使われ、44年8月15日から地下壕が構築されていきました。45年の1月になると艦政本部地下壕が掘られ、日吉の街は海軍の軍人や軍の施設を作る作業員がきて、さながら軍都の様相を呈していきました。
戦況が悪化する中で連合艦隊司令部が旗艦大淀から日吉キャンパスにある谷口吉郎が設計したモダンな学生寮に入ったのは44年9月29日でした。司令部地下壕はまだ建設中で、一部使用可能になったのは11月になってからです。10月には「台湾沖航空戦」「レイテ沖海戦」、45年4月6日の戦艦「大和」の出撃命令などはこの日吉の司令部から発せられています。
今回は、このなかで見学が可能な旧帝国海軍連合艦隊司令部跡を見学し、戦争遺跡をとおして、戦争と国家について考えたいと思います。
行程
13:00 東横線日吉駅改札前 銀の玉集合
13:05 慶應義塾大学陸上競技場横へ移動
本日の見学についての説明等(15分+α)
13:30 移動(5分)
13:35 慶應義塾高校(旧大学予科第一校舎)校舎とレリーフ(5−10分)
13:45 移動(5分)
13:50 地下壕<連合艦隊司令部跡>(60分)通常、集合からだいたい50分で地下壕に入るそうです。
14:50 移動 (5分)15時前に地下壕から出る。
14:55 チャペル(5−10分)
15:05 前方あたりにある艦政本部地下壕説明(5分)
15:10 弥生式竪穴住居址と耐弾式竪穴抗(5−10分)
15:20 寄宿舎前(10−20分)15時30分前に寄宿舎前に到着する。
15:40 移動(10分)
15:50 質疑応答<使用可能であれば、ファカルティラウンジ職員食堂で>(40分)
16:30 終了
「海のむこう」を想像する ―旧帝国海軍連合艦隊司令部跡で考えたこと―新井(源河)葉子 ARAI (GENKA) Yoko

沖縄島南部の戦場跡に広がるさとうきび畑の風景に、沖縄戦で父を亡くした遺児の気持ちを重ねた名曲「さとうきび畑」。その歌詞に、「むかし海のむこうからいくさがやってきた」という一節がある。沖縄戦は地元からみればまさに「海のむこう」からやってきた禍であった。
今回の遠足は、沖縄を立ち位置に太平洋戦争を考えてきた私がこれまで持ち合わせていなかった視点を与えてくれた。以下に、その視点を整理してみたい。なお、この文章には私の個人史を特色づけるいくつかの要素――アメリカ統治下の沖縄に生まれたこと、沖縄戦を生きのびた世代から教育をうけたこと、勤務していた大学に米軍ヘリが墜落・炎上した現場に居合わせたこと――が多少なりとも影響していることを、予め記しておく。
2010年3月31日は、曇りで肌寒い天気となった。日吉台地下壕保存の会(以下「保存会」)の皆さんの案内で慶応大学日吉キャンパスに残された旧帝国海軍の痕跡(軍の利用に供された校舎など)を見ながら、グラウンド脇にある壕入口に向かった。壕入口のドアは、ゆるやかな下り坂の坑道へと続く。懐中電灯の明かりをたよりに、足元の水溜りに注意して歩いた。湿り気を帯びひんやりとした空気からか、内部がコンクリートで塗り固められた坑内の様子からか、沖縄島の小禄(おろく)にある旧海軍司令部壕のことを思い出した。日吉、小禄のいずれの壕も帝国海軍が1944年8月に着工した壕であるから、設計の要素には類似点もあるようだ。しかし今回の見学では、これらの壕の類似よりも、相違を決定づける二つの要素が印象に残った。
まず規模である。小禄の壕が延長450メートル程度であるのに対し、この日吉の壕は延長1200メートルと三倍近い長さがある。また、小禄の壕の作戦室が約28立方メートル(幅2.5m×奥行き4.9m×高さ2.25m)であるのに対し、日吉の壕の作戦室は240立方メートル(幅4m×奥行き20m×高さ3m)と、十倍近い広さを持つ。坑道の幅も、人がすれ違うと肩が触れ合うような小禄の壕(1.5〜2m)に比べ、日吉の壕は4〜5人が横に並んで歩ける広さである。ところで、小禄の壕を見学したときはコンクリートの内装を見て、整備されているとの印象を受けたが、それは、沖縄に残る土壁の陸軍壕(司令部壕・病院壕)やガマ(自然の洞窟を利用した避難壕)との比較で見たためであった。今回日吉の壕の規模を見て、小禄の壕は司令部壕とはいっても所詮“出先機関”に過ぎなかったことを知った。
もう一つの決定的な違いは、壕内における“死”の有無である。小禄の壕では1945年6月11日に米軍の集中攻撃が加えられた結果、多数の将兵が命を落とした。戦後、壕内からは2300体以上の遺骨が収集されたという。沖縄に配備された海軍の指揮を執った大田實司令官はこの戦闘で自決したが、死を覚悟した6月6日、海軍次官あてに「沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」の文言を含む電文を送っていた。各地の通信隊でも傍受されていたこの電文を、東京通信隊は7日に受信、9日に訳了した。東京通信隊は当時連合艦隊司令部の配下にあった。よって、大田司令官の電文はここ日吉に届けられたとみてよいだろう。日吉壕の電信室と暗号室を前に、保存会の案内役の方が、無線信号を傍受していた元通信兵の証言を織り込んで解説をしてくれた。鹿児島県鹿屋基地から出撃した特攻機は、沖縄近海の米艦船に近づくと信号音を出しっぱなしにして体当たり攻撃を行なったという。通信兵がその「ツー」という信号音を傍受し、そしてその音が途絶えたときに攻撃の終了、すなわち隊員の死を知ったのだった。壕内で戦死者を出すことのなかった日吉は、小禄の壕や沖縄島沖の米艦船など日吉からみれば「海のむこう」の戦闘現場から続々と届く死の報せを受信した場所だったのだ。
冒頭で触れた「さとうきび畑」は、戦争を沖縄にもたらした主体を「海のむこう」と抽象化し失った父への思慕を綴る。ざわわざわわ、と風の通り過ぎるさとうきび畑のある沖縄からみた「海のむこう」とは、派兵を命じ戦局を把握し戦果を分析していた日米それぞれの場所であったが、今回の遠足で、日吉の海軍司令部壕もそのような場所のひとつであったと実感した。
米軍ヘリが沖縄国際大学に墜落し炎上したことも普天間基地の移設問題も、沖縄に米軍基地をもたらしたあの「いくさ」が原因である。大田實司令官の電文の内容を反芻しながらいまだに軽減されない沖縄の基地負担を日本全体の問題として考える場所として、日吉の旧帝国海軍連合艦隊司令部跡ほどふさわしい場所はないかも知れない。
写真1 慶応義塾・第一校舎前。壁面に埋め込まれたレリーフ(写真2)と、日本を中心にしたアジア太平洋の地図がデザインされたカップ状のオブジェに注目。

写真2 慶応義塾の校章の左右に校舎の建設年が西暦(1934年)と皇紀(2594年)で記されたレリーフ。

写真3 壕の見学を終え、坑道を外にむかう。