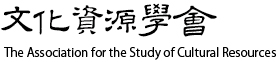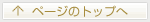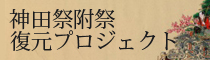第5回 早春の遠足 「鎌倉・葉山」
日程
- 2004年3月14日(日)
案内人
- 稲庭彩和子(神奈川県立近代美術館)
解説
- 酒井忠康(神奈川県立近代美術館館長)、太田泰人(神奈川県立近代美術館)、木下直之(東京大学)

今からおよそ50年前に日本初の近代美術館として誕生した神奈川県立近代美術館鎌倉館と、最新型の公立美術館として誕生したばかりの同葉山館を見学します。葉山館は美術館ではじめてPFI方式を取り入れました。活動・運営・建築を、それぞれの土地の歴史や記憶をたどりつつご案内します。
行程

- 10:30 神奈川県立近代美術館 鎌倉エントランス集合
- 10:35 近代美術館の歴史とその建築(解説)
- 11:15 「松本竣介・麻生三郎展」見学(自由見学)
- 12:00 近代美術館50年回想、初期の活動とその役割(解説)
- 12:40 昼食のためにいったん解散
- 14:10 JR逗子駅集合
- 14:17 バス停3番乗り場「海岸回り葉山行き」のバス発車時刻
- 14:40 葉山館着 葉山館案内
- 15:00 開館記念展第2弾「ベン・ニコルソン展」(自由見学)
- 15:40 美術館建築およびPFI事業(解説)
- 16:30 美術館教育プログラムについて(解説)
- 17:00 解散
鎌倉と葉山木下直之(東京大学)
1950年正月の創刊からしばらくの間、本誌『芸術新潮』のどの号のどの頁を開いても、武器を捨て、文化の国として出直そうとする日本人の熱い思いが伝わってくる。紙も図版も粗末だが、まるで日本国憲法前文のように前向きで、流行歌「青い山脈」のように明るい。まさしく「国破れて芸術新潮あり」という感じなのだ。
占領下に建設の準備が進み、サンフランシスコ講和条約が結ばれた直後、すなわち1951年11月に開館した神奈川県立近代美術館も、そうした時代の産物にほかならない。
鎌倉の鶴岡八幡宮の境内が建設地に選ばれたことにも、それはよく表れている。敷地を提供してまで、八幡宮が美術館を誘致したという。何といっても八幡は戦の神様(だからこそ頼朝が信仰した)、どうしても境内に文化の「神殿」が必要だった。
開館を前に、本誌は二度にわたってこの美術館を大きく取り上げた。まず3月号に建物を設計した坂倉準三が「鎌倉の現代美術館」を、ついで7月号に初代副館長となる土方定一が「近代美術館創生期」を書いている。
やがて誕生する美術館の名前はどちらでもよかった。むしろ近代とはすなわち現代、美術館に対するふたりの認識は、それが評価の定まった美術を並べる場所ではなく、新たに美術を生み出してゆく場所だという点で一致していた。
「美術館が傑作の墓場であることは我慢するが、駄作の墓場になつてはかなわない」という土方は国立博物館をこき下ろし、坂倉はオランダのある美術館館長のこんな言葉を引用する。「この美術館に入る者は美術について知つて居たすべてのことを忘れ、美術館より出る者は美術について考え始める」
そうして建設された建物を八幡宮境内に残して、昨年秋に神奈川県立近代美術館は葉山に展開、「もうひとつの現代展」で新たな美術館・葉山館を開館させた。一方の鎌倉館はどうなるのかと心配した。この機会に、手のひらを返したように、八幡宮から追い出されてしまうのではないかという心配もそこには含まれていた。半世紀前に提供された敷地は借地だったからだ。しかし、こちらも少し遅れて、「堀内正和の世界展」で無事再開した。
このふたつの美術館は、池畔と海辺の違いはあるものの、どちらも水際に建っている。それぞれの環境をどう取り込むのかが課題であった。葉山館の展示室からは、大きな窓を通して海が見える。しかし近寄ると、ガラスを二重にはめ込んだ窓の「厚さ」に驚かされる。透明性は保証するが外気は絶対に入れないという、飛行機や新幹線の窓に似ている。一見開かれてはいるが、実は閉ざされている。潮風ほど美術品に悪いものはないからだ。
一方の鎌倉館は窓を必要としなかった。建物が池に張り出し、水面を吹いた風はそのまま中庭へと流れ込んでくる。そして驚くべきことに、かつては、彫刻だけでなく絵画までもがそこに展示されていた。こちらは、窓を開けたままで走った昔の汽車に似ているかもしれない。「身体のコンディション、精神のコンディションが非常にいい条件のもとで見ることは大切」と考えた坂倉は、美術館を、美術品の都合にではなく、そこを訪れる人間の都合に合わせたからだ。
坂倉が頭に描いたその人間とは、創刊間もない『芸術新潮』の読者でもある。素朴なかつての『芸術新潮』と豪華な昨今の『芸術新潮』とは、鎌倉館と葉山館のそれぞれの佇まいに似ていなくもない。